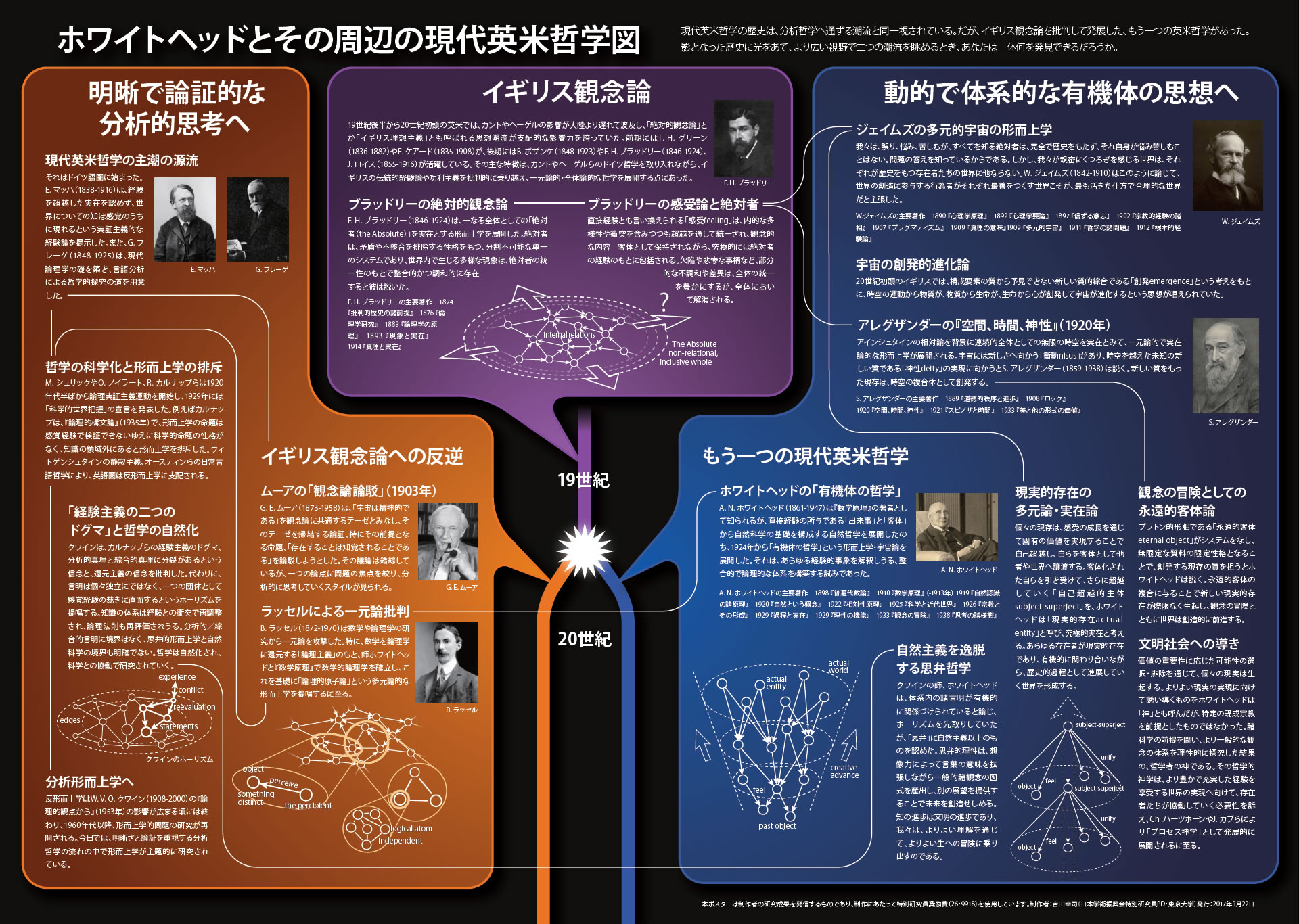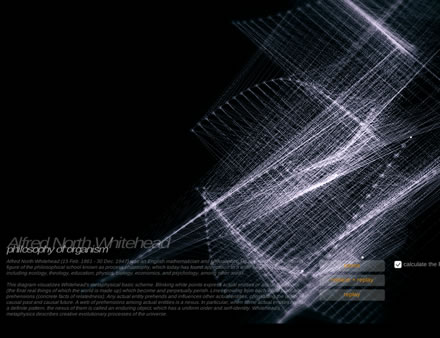ローウェル講義における経験・主体(性)の位置づけ
中期哲学では「知るものと知られるものの総合は形而上学に委ねる」(CN 28)といっていたホワイトヘッドは、最初の形而上学的著作『科学と近代世界』では「知るもの」の考察を含む形而上学体系を展開しています。ですが、この著作のどの構成段階で、後期哲学固有の立場になったのかは解釈上の論点となってきました。本節では諸解釈を整理しながらホワイトヘッドの記述を精査し、前節の区別をもとにローウェル講義の立場を明らかにします。
|
抱握の発展史的起源
|
|
| aa |
中期やローウェル講義とは異なる後期哲学固有の特徴として汎主体主義を挙げるフォードは、もちろん、ローウェル講義を汎主体主義として解釈していません。フォードによれば、ローウェル講義では汎主体性は未だ定式化されておらず、主体性は、高度に進化した存続的客体である複雑な有機体のみに帰せられていました。それどころか、あとで付加された箇所ですら心的機能をもつのは「完全な現実的生起complete actual occasion」のみに制限されていることから、フォードは『科学と近代世界』全体について汎主体主義を認めていないようにも読めます。 ただ、ここで否定されている汎主体主義とは、前節の区別にしたがっていえば、汎心主義、すなわち狭義の汎主体主義のことでしょう。単なる用語法の食い違いを避けるため、まずは前節で区別した意味での汎経験主義がローウェル講義で認められるかどうかを最初に議論します。 前節の(i)でみた通り、中期のホワイトヘッドは意味づけが経験であるとして、経験を知覚しつつある身体的出来事と他の諸出来事との関係のうちに見出そうとしていました。ただし、中期哲学においてこの経験は、人間の知覚しつつある身体的出来事についてのみ語られていました。汎経験主義といえるためには、能動的な経験の働きが自然内の出来事すべてに一般化されていなければならないでしょう。 中期哲学に引き続きローウェル講義でも、ホワイトヘッドは、『自然認識の諸原理』で引用した『アルシフロン』の箇所を取り上げますが、今度はさらに、科学的唯物論への先駆的批判者としてもバークリーを評価しています。科学的唯物論は、「単に位置を占める」物質に究極的実在をみていましたが、バークリーは、経験を関係のうちに捉え、科学的唯物論の批判者になっていたというのです。ホワイトヘッドは、ローウェル講義ではさらに、バークリーに言及しながら、「抱握的統一化の過程a process of prehensive unification」という独自の考えを展開するに至っています 。すなわち、ホワイトヘッドが独自に解釈するところ、バークリーにとって「自然的諸存在の実現realisationを成立させるものは、統一体をなす心のうちで知覚されてあることthe being perceivedである」(SMW 69)。つまり、事物が存在することは、事物がそれ自体として存在することではなく、今・ここという立脚点から見られたそれとして心において実現されていることです。『アルシフロン』の例を用いれば、城や雲、惑星は、あるとき・ある場所に単に位置を占めてそれ自体として存在するのではありません。今・ここという立脚点から見られた、向こうの城、雲、惑星が、今・ここの心において取りまとめられ知覚されてあるのです。ホワイトヘッドはバークリーの哲学をこのように解釈して、バークリーの心に代替される「抱握的統一化の過程a process of prehensive unification」という自説を提示します(SMW 69)。 後期ホワイトヘッド哲学における基本用語ともなる抱握とは、意識を必ずしも前提しない非認識的把握uncognitive apprehensionです。中期哲学では、意味づけが経験であり、意味づけとは関係づけられてあることの認識でしたが、ローウェル講義における「実現」は「諸々の事物を抱握の統一体へ集めること」(SMW 69)であるとされ、認識における動的な過程とその統一性が強調されています。実現は、他の事物との関係に尽きず、時間的にも空間的にも他の諸事物と本質的な連関をもちながら、それらを一つの今・ここa here and a nowにおける統一体に限定することなのです。 『科学と近代世界』の第4章「18世紀」によると、“apprehension”には意識が含意されることもあるから、必ずしも意識を含まない用語として“prehension”という術語が採用されました。『科学と近代世界』ではこれ以上の説明がないのですが、のちに『観念の冒険』では、ライプニッツの「統覚apperception」の用法を参照して抱握の用法が説明されています(AI 234)。すなわち、ホワイトヘッドによれば、ライプニッツは、意識を含むわけではない「知覚perception」に接頭辞apを加えて統覚apperceptionという用語を用いたのだが、これらの用語は「意識consciousness」という考えに密接に結びついているばかりか、ホワイトヘッドが拒否する「表象的知覚representative perception」という考えにも巻き込まれてしまっています。そこでホワイトヘッドは、ライプニッツとは逆に“apprehension”からapを取り去り“prehension”という術語を用いるというのです。つまり、意識とか表象的知覚を暗示することなく、意識を伴う以前の非認識的把握を一般に表現する術語として抱握が採用されたというわけです。『過程と実在』では、「意識は経験を前提するが、経験は意識を前提しない」(PR 53)と述べられるように、意識的経験は、抱握としての経験のある高次の相において成立するに過ぎません 。 また、『科学と近代世界』の第3章「天才の世紀」では、抱握という発想に関連してF. ベーコンに言及されています。ベーコンの後継者たちは物質を「力によって外的に動かされる受動的物質」とみなしましたが、ベーコン自身は物質を単に受動的なものとみなした科学的唯物論よりも根源的な真理をみていました(SMW 42)。ホワイトヘッドはベーコンをこのように評価し、『森の森』から次の文章を引用しています 。
ホワイトヘッドの理解するところ、ここで覚識は「認識的経験cognitive experience」を意味し、知覚は「評価taking account of」を意味しています。抱握は、認識的経験をもたないにせよ、評価という意味合いとしての“perception”を継承する用語でもあります 。 さて、抱握という用語の由来について以上のような箇所を参照すると、ローウェル講義の時点でホワイトヘッドの形而上学は、前節で区別した意味で汎経験主義と呼べると思われます。というのも、ローウェル講義では既に、あらゆる出来事が、意識的な経験・反省的な認識をもたなくとも、意識成立以前の関係において他の出来事を抱握するとは考えられていました。あらゆる出来事が他の出来事を抱握する以上、出来事は一般に、能動的な評価という意味での経験を有していると考えられます。つまり、身体的出来事の能動的な経験という中期哲学の考えが、ローウェル講義では自然内の出来事すべてに一般化されていると解釈できるのです。 汎経験主義という用語を使うグリフィンも、自己目的的に実現する出来事の内的価値(SMW 93)、人間的生で了解する価値との類比(SMW 93)、バークリーやロマン派への賛同を論拠に挙げた上で 、ベーコンを参照して定義される抱握は汎経験主義に他ならないと解釈しています。また、出来事がもつ内的実在性interiorityや、自己目的的な価値実現という点に関してはフォードも広義の汎主体主義として同意しているところです(EWM 42) 。したがって、用語上、前節で区別した、意味づけとしての能動的な経験をもつという意味でなら、ローウェル講義は汎経験主義(すなわち広義の汎主体主義)であったということができるでしょう。 問題は、ローウェル講義で、意識的経験を含むような主体や心がどのように形而上学体系内に位置づけられていたかということです。グリフィンは、「生理学の結果は心を自然の中に戻すことだった」(SMW 148)とホワイトヘッドがいい、我々自身の心理領域が「我々の身体的出来事の自己認識」(SMW 73)であるといっていることから、ローウェル講義も汎心主義と呼びえたと解釈しています 。ですが、この点に関して、グリフィンを批判しフォードを擁護するカブの議論は極めて説得力があります。カブはまずローウェル講義における主体性という用語は認識 を含意すると分析した上で、主体性は出来事すべてに一般化されていないと主張します。ローウェル講義では「暫定的実在論」の立場がとられ、「感覚世界はすべての観察者に共通で、それゆえ我々がそれを認識するのに依存していない」 。我々の認識経験は身体に依存し、それは根源的には身体的出来事の経験であるのですが、この身体的出来事はそれ自身のうちに宇宙の全諸相を統一しており、我々の認識とは独立に実在的です。また、ホワイトヘッドは、知覚は認識的把握を含意し、抱握は非認識的把握であるとした上で(SMW 69)、「知覚は抱握の認識である」(SMW 71)というから、抱握的統一化は、知覚ないし認識とは独立に実在的であることになります。このように分析した上でカブは、「共通世界の第二性質」(SMW 91)を含む身体的出来事は自然内の出来事すべてに一般化されたが、認識経験は人間に制限されていたと解釈します 。 こうしたカブの解釈は、(自己認識を含意するような)主体性や心性は高度に進化した存続する客体である複雑な有機体に帰せられていたというフォードの解釈を支持することになります。ホワイトヘッド自身のテキストに即する限り、カブの解釈する通り、主体性や心性は人間など複雑な有機体に制限されていたと解釈されなければならないでしょう。 ただ、筆者は、カブの解釈にも、一つ議論されるべき問題があると思います。それは、グリフィンがローウェル講義における汎経験主義を主張する際に挙げる論拠の一つ、すなわちライプニッツ哲学に関してホワイトヘッドが論及している文脈に関してです。 ローウェル講義における汎経験主義を主張する際にグリフィンは、上で挙げた論拠の他に、ホワイトヘッドがライプニッツを批判する文脈を強い論拠として挙げています(SMW 155)。「科学と哲学」の章でホワイトヘッドはライプニッツを批判し、「彼は経験の単位unitとしての出来事を、それが安定して重要性を担う存続的有機体や、個体化の成長した完全性increased completeness of individualizationを表している認識的有機体cognitive organismとも区別しなかった」(SMW 155)と言っています。ライプニッツ解釈の正当性はさておき、グリフィンは、ホワイトヘッドがこの問題を解決しようとしたのであればすべての出来事に経験が帰されたと解釈します。すなわち、認識的な心性の有無にかかわらず、主体的経験を欠いた出来事はないという汎経験主義はローウェル講義に見出されるというのです 。 ところがカブはグリフィンのこの主張を批判します。カブによれば、モナドは「継起する諸経験を伴った主体」ですが、ホワイトヘッドが批判するのは、実体‐属性図式を保持したために「どのように諸モナドが内的関係によって構成されるか」をライプニッツは説明できなかったという点です 。つまり、モナドが経験する、あるいは経験によって構成されることについて批判が向けられているのではないから、出来事は経験すると修正したと解するべきではありません。むしろここで経験という用語は批判的文脈で使われているのであり、加えて、ライプニッツのモナドは「時空内の統一された出来事」に格下げされているのですから(SMW 65, 70)、ホワイトヘッドは明確には出来事に経験を帰さなかったとカブは解釈します 。 確かに、出来事が「時空内の統一された出来事」の「体積volume」に格下げされているのだとしたら、出来事に主体性が帰せられていたと解するべきではないでしょう。すべてのモナドが表象をもつようにすべての出来事が抱握をもつといえても、出来事が時空的な体積に過ぎないならば、出来事の抱握には心的作用が含まれているとはいえないかもしれません。 もっとも、カブも、「共通世界の第二性質」(SMW 91)を含む身体的出来事は、自然内の出来事すべてに一般化されたと解釈しているから、意味づけが経験であるという前節で区別した意味でならローウェル講義における汎経験主義に同意するでしょう。この限りで、ローウェル講義における汎経験主義は堅持することができます。また、ローウェル講義での主体性の用法は認識を含意し、主体性が出来事すべてに一般化されていないというカブの解釈を採っても、その解釈と、前節で区別した意味での汎経験主義は両立します。 ですが、ここまでは譲歩するにしても、筆者は、ライプニッツ哲学を批判する先の箇所は、ホワイトヘッドが、ローウェル講義後に、主体性や認識経験を自身の形而上学体系内に位置づける際に重要な箇所であったと解釈します。なるほど、フォードやカブも指摘する通り、ローウェル講義で主体性は、認識経験を含意し、人間など複雑な有機体のみに関わり自然内の出来事すべてには一般化されていません。出来事は他の出来事を抱握するにしても、抱握は他の出来事と関係づけられ意味づけられているという程度の意味で、すべての出来事について抱握が心的作用を、ましてや反省を伴う認識を含んでいるとは言えません。ローウェル講義でホワイトヘッドは、「心的認識は、ある全体の反省的reflective経験であって、一つの統一的現象unit occurrenceとしてそれが自体的に何であるかを自らに対して報知するものとみられる」(SMW 148)と述べていますが、ここでの心的認識および対自的自己関係は、自然内の出来事一般について語られているわけではなく、人間のような複雑な有機体の出来事についてだけ語られていると思われます。 しかし、次節でみるように、ローウェル講義以降、どのようにホワイトヘッドが主体性や認識を自らの体系内に位置づけていったかを視野に入れるとき、筆者は、ライプニッツ哲学の批判的受容が本質的な寄与をなしたと解釈します。前節で分析したようにホワイトヘッドは、時間や空間、実体的物質の伝統的理解を批判することを通して、アリストテレス以来の実体‐属性や主体‐客体という伝統的図式を出来事‐客体という図式へ鋳直そうとしていました。前章では、出来事はその内的実在性において他の出来事を統一する一方で、外的実在性において他の出来事のうちに反復されるというホワイトヘッドの出来事論がライプニッツのモナド論に近いことを指摘しましたが、このような出来事論のもと、ライプニッツ哲学の批判的受容を介して伝統的な主体‐客体図式を打破していったと解釈できると思います。 次節では、ローウェル講義との連続性を堅持しながら、ローウェル講義後に行われたハーヴァード講義、『科学と近代世界』刊行時に加筆された箇所を頼りに、過渡期ホワイトヘッド哲学における主体について検討することにします。 |