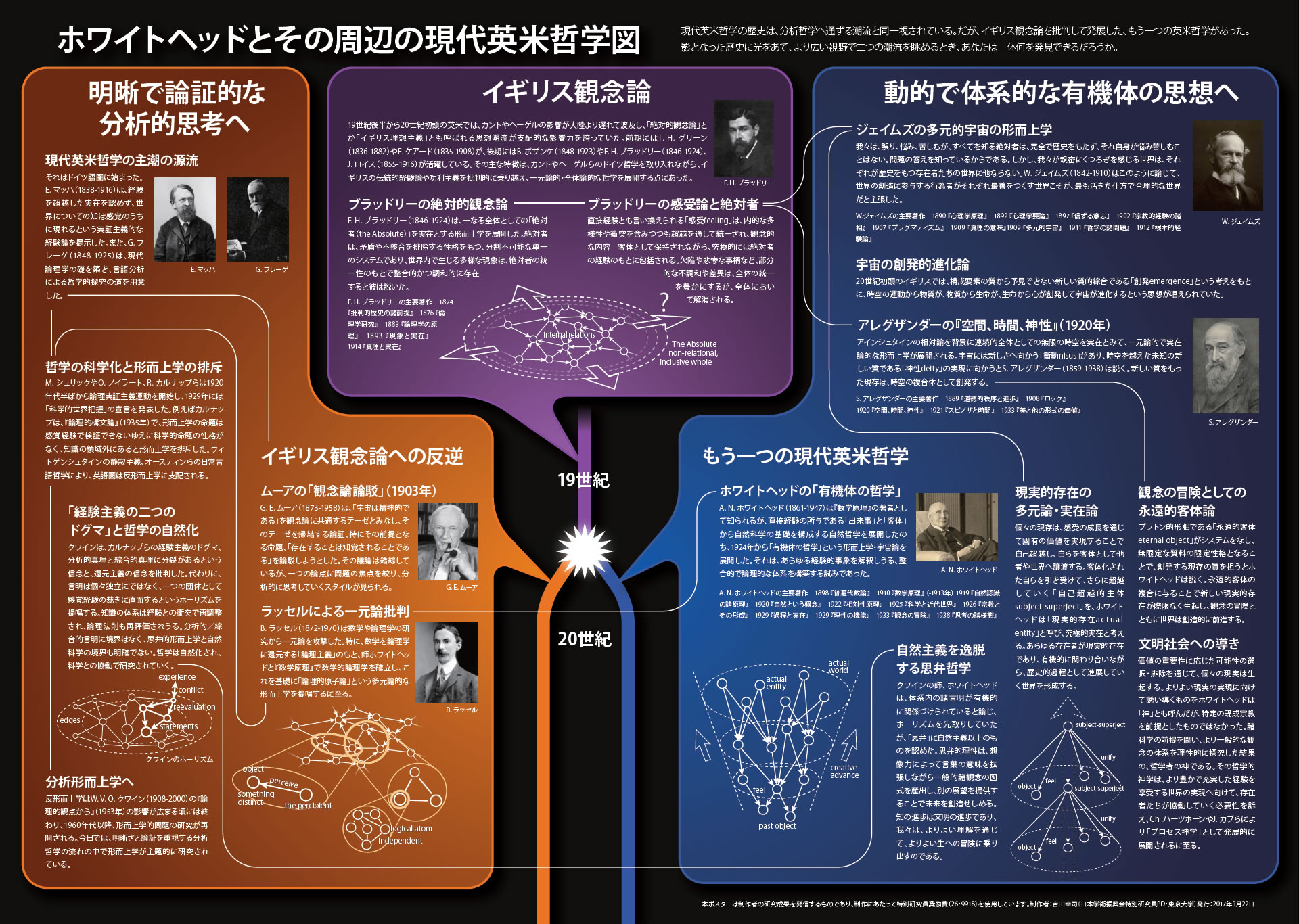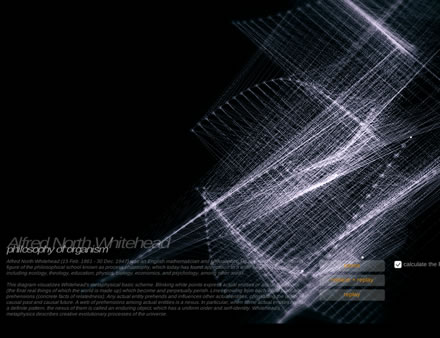中期哲学における「経験」「主体」「心」
あらゆる存在が主体であるという後期ホワイトヘッド哲学の思想を特徴づけるのに、いくつかの用語が使われています。例えば、『科学と近代世界』の発展史研究においてフォードは、汎主体主義という用語を使って、中期やローウェル講義の哲学とは区別される後期哲学を特徴づけています。しかし、この用語自体はホワイトヘッドが使った用語ではないばかりか、グリフィンも指摘する通り、フォードの用語法は些か錯綜しています。しばしばフォードはすべての現実的生起が心性をもつという「汎心主義panpsychism」を汎主体主義と呼びますが、グリフィンは、これを狭義の汎主体主義として分類します。これに対してグリフィンは、「主体的経験を欠いた空虚な現実性」(PR 167)はないという広義の汎主体主義を狭義の汎主体主義から区別し、これをグリフィン自身の好む用語で汎経験主義と呼びます。つまり、汎心主義(狭義の汎主体主義)は、あらゆる存在が物的極だけでなく心的極をもつことを意味するのに対して、汎経験主義(広義の汎主体主義)は、心的でなくとも、あらゆる存在が能動的な働きをもつことを意味します。
しかしながら、汎心主義という用語の方には注意が必要です。『過程と実在』においてホワイトヘッドは、諸々の与件を綜合統一する働き、およびその働きから生じる統一体として心mindという言葉を用います。特に『過程と実在』でロックやヒュームに言及して心について論じるときには、それを主体と言い換えたり、意識的と形容したりしているように(PR 138f.)、心は、近代における主体概念や意識的な自我を含意していると考えられます 。ですが、ホワイトヘッドは、すべての存在が意識的であることを主張していたわけではなく、この意味での汎心主義はホワイトヘッドの念頭にはありませんでした。
むしろ、フォードの“panpsychism”が意味するのは、あらゆる存在が心性mentalityをもつということでなければなりません。心性は、観念的なもの(永遠的客体)の感受であって、心とは区別されます。それは、新しさを現実の世界に実現していく作用でもあり、意識をもたない原初的な形態の存在にもあると考えられます。汎心主義があるとすればこの意味でなければなりませんが、この点についてカブは、“psyche”という用語は「魂soul」のギリシア語であって、後期ホワイトヘッドにとって重要な用語であるから、フォードの狭義の汎主体主義、すなわち汎心主義に対して“panmentalism”という用語を提唱しています。
したがって、ホワイトヘッド哲学の発展史を跡づけるとき、第一に汎経験主義(広義の汎主体主義)が、第二に“panmentalism”としての汎心主義(狭義の汎主体主義)が、どの段階で説かれるようになったかが論争点となりうるのです。もっとも、汎心主義の方については、ホワイトヘッドはその前段階として、自身の立場から心を捉え直そうとしていたとみえます。そのため、過渡期哲学に制限する場合、また、現実的生起や結合体の発展史的起源を明らかにするという目的のためには、まず汎経験主義が発展史のどの段階で見出されるか、次いで、ホワイトヘッドが自身の哲学においてどのように意識的な経験を含む主体や心を位置づけていったかが問題となります 。
以下、まずは、中期哲学における「経験」「主体」「心」についてそれぞれ順にみていくことにしましょう。
|
―用語の区別とその分析―
|
|
| aa |
(i)経験について 前章までに既にみた通り、中期の自然哲学は、自然内で「知覚されるものthe perceived」ないしは「知られるものthe known」のみを考察しているのでした。すなわち自然哲学において「我々は自然のみを問題にしている。つまり、知るものと知られるものとの総合ではなく、知覚的認識の対象を問題にしているのである」(PNK vii)。中期のホワイトヘッドは、「知覚するものthe perceiver」ないしは「知るものthe knower」を自然哲学の範囲外とし、「知るものと知られるものの総合は形而上学に委ねる」(CN 28)と述べています。中期哲学は、自然内に見出されない認識主体や意識等を除外し、自然内部で知られるもののみに議論を制限しているのです。 このように、自然とは異質的な意識等を含むことなく同じタイプの自然内の要素をそれら自体の間で関係づけて考えるとき、自然について同質的にhomogeneously考えているといわれます(PNK 60, CN 3)。自然哲学や自然科学はもっぱらこの同質的考察に関わっています。同質的思考に対して、異なるタイプの要素(例えば意識や神、自由意志など)を関係づけて考えるとき、我々は自然について異質的heterogeneouslyに考えているといわれます(PNK 60)。中期の哲学は異質的考察を持ち込まず、自然内で知られるもののみを同質的に考察します。 『自然認識の諸原理』という表題にもある「自然認識」も、自然内の同質的な要素間で成立する認識を指しており、その著作の第1章では、バークリーとカントに言及して、「経験」について定義されています 。ホワイトヘッドは、『アルシフロン』の第4対話の第9節を引用して、バークリーが認識を関係性として捉えたことを評価しています(PNK 9f.) 。その箇所では、アルシフロンが、離れたところから見たとき城のドアや窓、胸壁を区別できず小さな丸い塔しか見えないと言っているのに対して、そこに行ったことのあるユーフラノーは、それが小さな丸い塔ではなく胸壁ややぐらのある大きな四角い建物だと知っていると言っています。惑星や雲についても類似したことが指摘されたあと、「したがって、あなたがここで見ている城も惑星も雲も、遠くに存在するとあなたが想定している実在的なものでないことは明らかではないか」とユーフラノーは主張します。ホワイトヘッドが評価するのは、この箇所でバークリーが、あるとき・ある場所にそれ自体として存在するものを否定し、見ている今・こことの関係性が認識において本質的に関わると考えていた点です。 もっとも、意味づけから分離されうる与えられたものの経験を想定したことによってバークリーが主観主義的観念論へと導かれていったことにはホワイトヘッドは賛同せず、この点については、バークリーを逆転して「意味づけが経験である」(PNK 12)としたカントに賛同しています。ここで「意味づけとは諸事物が関係づけられてあることrelatedness[を認識すること]」(PNK 12)であり、自然認識は、知覚しつつある出来事(知覚者の出来事)percipient eventと自然内の他の諸出来事との関係において生じると捉えられています。つまり、カントに賛同しているといっても、認識が、知覚する側の意味づけなしには成立しないという点であり、ホワイトヘッドは、(判断や推論を含まない限りの)自然認識を、アプリオリな認識能力によってではなく、自然内の出来事同士の関係として捉えようとしています。知覚しつつある出来事は身体的出来事であり、それは自然内の出来事であるから、中期哲学において理解される自然認識は自然内の同質的な要素同士の関係なのです。 この知覚しつつある出来事は、単に受動的で静的な一要因ではありません。ホワイトヘッドは次のようにいいます。
中期哲学でも既に、自然認識は、「創造的前進」とも換言される自然の推移において、知覚しつつある出来事と自然内の諸出来事とが動的に相互に関係づけられることによって生じると考えられていました。意味づけとしての経験が、感覚与件を単に受容する受動的な経験とは理解されず、また、身体的出来事である知覚しつつある出来事のうちに経験の能動性が見出されていたことは特筆に値します。中期哲学ではまだ、意味づけとしての経験は自然内の出来事すべてに一般化されていませんが、ローウェル講義では、それがすべての出来事に一般化されます。この点は次節で扱うことになるでしょう。 (ii)主体について しかし、経験という用語については中期で言及されているのに対して、主体という用語については独自の用法が与えられているわけではありません。そもそもホワイトヘッドは伝統的な主体という概念には批判的であり、後期哲学においても「主体主義原理」は「再定式化」されて論じられ、主体は常に「自己超越的主体subject-superject」の省略形として理解されています 。そのため正確には、いつ汎主体主義が採用されるに至ったかと問うのは誤解を招く問いかけであり、むしろ伝統的な主体‐客体図式を解体してどのように独自の立場が打ち立てられていったのかが問題の焦点となるべきでしょう。 このように問題を立て直すとき、その試みは、時間や空間、物質といった自然科学の基本的概念を鋳直す中で中期から遂行されつつありました。 ホワイトヘッドは古代ギリシアの哲学・思想にまで遡って、近代科学の物質という概念の起源をアリストテレス以来の実体概念のうちに見出します。ホワイトヘッドによれば、アリストテレスは、その論理学において述語を主語に帰属させ、感覚的に覚知されるものの下に「もはや他の何ものにも述語づけられない究極的基体substratum」としての実体を措定する傾向を作り出しました。近代科学の物質の起源もここに見出されます(CN 18)。ホワイトヘッドの分析するところ、当時の電磁気学および相対性理論におけるエーテルを含め、物質は、本来は思考の抽象物に過ぎない裸の個体的存在として、自然の形而上学的基体という地位を担い、諸属性はそれに帰属させられました。アリストテレスの哲学において時間や空間は属性ですが、それにもかかわらず科学者は基体であるはずの物質を時間や空間のうちに前提し、物質が空間内を運動変化するとみなして混乱しました。 これに対してホワイトヘッドは、我々が空間に見出すのは、バラの赤さやジャスミンの匂い、大砲の音であり、「空間にあるのは実体ではなく諸属性である」といって科学者の混乱を批判します。我々が直接経験しているのは属性間の関係なのであって、「空間は実体間の関係ではなくして属性間の関係である」と自らの見解を提示するのです(CN 21)。 ところで、中期哲学において時間や空間は出来事から抽象されるという意味では出来事は時間・空間そのものであるといってもよいのでした 。バラの赤さやジャスミンの匂いは出来事そのものではありませんが、感覚的客体として、それらの状況たる出来事に「進入」します。したがって強いて基体という用語を当てはめようとするなら、それは出来事に当てはまりますが、出来事は時間・空間そのものなのですから、時間や空間を出来事に帰属させる必要はありません。しかも自然内の究極的事実は出来事でありその背後に遡ることはできないのですから、無論、出来事が帰属させられるところの基体も存在しません。また、物質を基体としながら、それを時空の中に位置づけるという混乱もありません。時間や空間は出来事間の関係であり、客体が出来事に進入する限りでそれらは属性間の関係であるということもできます。既に中期においてホワイトヘッドは、主体‐客体ではなく出来事‐客体という図式のもと、諸属性が帰せられるところの基体よりも、むしろ属性や関係に重点をおいた自然哲学を構築していました。 出来事‐客体という図式は、近代における「自然の二元分裂論theories of the bifurcation of nature」の批判としても強みを発揮します。自然の二元分裂論とは、物質からなる原因的自然causal natureと、色や匂いといったいわば第二性質からなる我々に立ち現れる自然apparent natureという二つの実在へと自然を分離するような近代の諸理論を指します。ホワイトヘッドによれば、そのような諸理論では、二つの自然は心において出会うことになります。つまり我々の心が、物質からなる自然に、赤さや暖かさといった第二性質の心的要素を付加することによって、知覚的世界は立ち現れると考えられることになります。ホワイトヘッドは、このような自然観は近代科学・近代哲学に悲劇的な影響をもたらし、「自然と心の関係という大問題を、人間の身体と心の相互作用というちっぽけな形態に変容してしまった」(CN 27)と非難します。出来事‐客体という図式の強みは、こうした自然の二元分裂を生じさせない点にあります。というのも、出来事が自然内の要素であるのは言うまでもなく、色や匂いといった感覚的客体や、机やイスといった知覚的客体、分子や輻射エネルギーといった科学的客体もすべて自然内の要素であり、出来事‐客体図式において我々は、自然内で知覚されるこれら諸要素の関係として自然認識を議論することができるからです。 つまり自然の二元分裂論批判でもやはり関係の第一義性が強調され、「科学は認識の原因を議論しているのではなく、認識の整合性を議論している」(CN 41)と述べられます。しかも関係とは認識主観がもつアプリオリな範疇の一つではありません。それは自然内の諸要素の関係であって、それを理解しようとするところに自然科学や自然哲学の本分があります。直接経験として与えられるのは未分化の複合的事実であり、我々はそれを自然の様々なタイプの要素やそれらの関係へと分析するのであって、その逆ではありません。我々の感覚覚知sense-awarenessにおける直接的事実factは、バラバラの与件としてではなく、様々なタイプの要素へと分化されていない一つの複合的事実として経験されます。木々の緑や鳥たちの囀り、太陽の暖かさといった諸要因factorが個々バラバラにまず経験されてそれらの集合として事実が構成されたり統一されたりするのではなく、逆に、それら諸要因が未分化な複合的事実が直接に経験されているのです。一般に自然科学は、素粒子物理学などにみられるように、原子や電子といった複合性の低い要素から、複雑な自然現象を説明する試みだと受け取られているかもしれません。あるいは、原子や電子、それらを構成するクォークといった素粒子など、複雑な自然物を構成している単純な究極的実在の探求という了解もあるかもしれません。ですが、ホワイトヘッドの主張はむしろ逆である。我々に直接的に経験されている自然の究極的事実は複合的な未分化の事実であり、自然科学を含め、自然研究が実際に行っていることは、抽象化を通して様々なタイプの多様な諸存在へと分析することによって複合的な事実を整合的に説明することだというのです。 以上でみてきたことからもわかるように、中期でもホワイトヘッドは、伝統的な主体‐客体図式に対して批判的であり、アリストテレス的存在論とは異なり属性と関係を基礎に自然哲学を展開していました 。独自の後期哲学の立場が如何にして形成されたかは次節以下の課題ですが、さしあたり中期の哲学が伝統的な枠組みを鋳直すための足がかりとなっていたことは確かでしょう。 (iii)心について 最後に中期哲学における心の位置づけを探っておきましょう。(ii)でみた通り、心は、自然の二元分裂論では批判的文脈で言及されていましたが、別の箇所ではホワイトヘッド自身の積極的な主張を見出すことができます。 また、『自然認識の諸原理』の最終章や第2版の注釈では、「大雑把に言えば個体である、心的なものとしての知覚しつつある客体percipient object」は、「生きている有機体living organismがもつ経験の流動である知覚しつつある出来事」とは区別され、「『自然』の外にある」と考えられています(PNK 202; cf. PNK 197, 200) 。知覚しつつある出来事が、知覚しつつある客体の状況あるいは場所locusとして自然の推移のうちにあるのに対し、知覚しつつある客体は、再認しうる恒久的性格をもっています(PNK 83, 90f.)。ホワイトヘッドによれば、「この客体は覚知の統一体であり、その再認は、一連の知覚しつつある出来事を一つの意識と連合された自然的生命として分類することへ導く」(PNK 83)。 中期自然哲学では知覚者に関わる事柄はその考察範囲から除外されているため、これ以上の議論は展開されていないのですが、これらの箇所から、心、あるいは心的なものとしての知覚しつつある客体が、自然の推移のうちにはないと考えられていたことはわかります。心は、出来事ではなく、客体の一つ、しかも意識に関わる客体として位置づけられていたのです。 中期哲学では、「経験」「主体」「心」が以上のように論じられていましたが、経験は出来事すべてに一般化されていないし、主体や心については十分に議論が展開されていませんでした。次節以下では、ローウェル講義、1925年ハーヴァード講義、『科学と近代世界』刊行に際して加筆された箇所でこれらがどのように進展していくのかをみていきましょう。 |