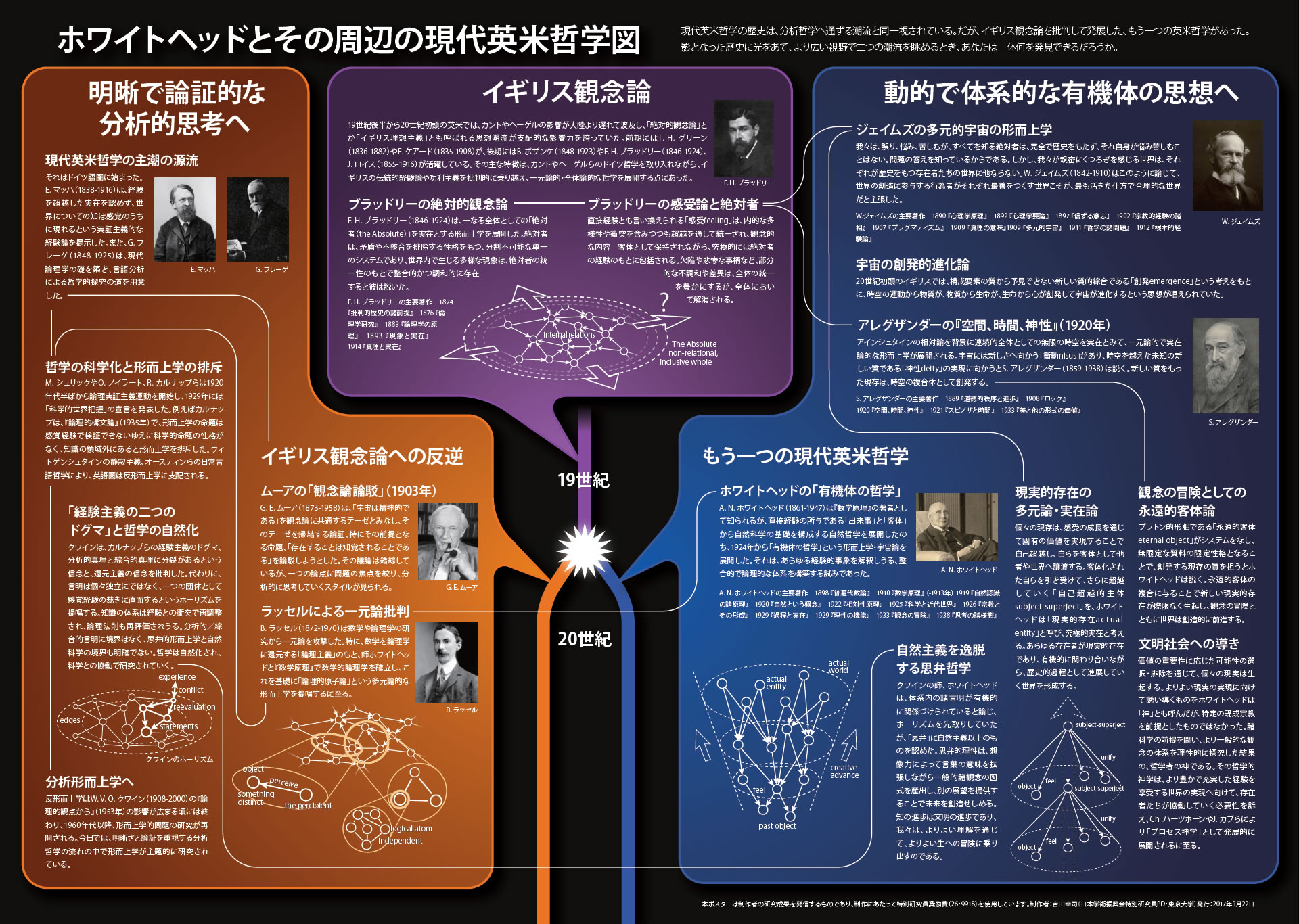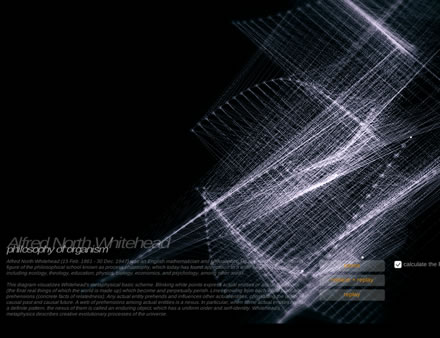出来事の個体性と量子論
中期自然哲学で、出来事は、無限に分割可能であると考えられていたのに対して、『科学と近代世界』では、出来事に個体性=分割不可能性(individuality)があると考えられています。この点に関して、フォードは、『科学と近代世界』を執筆中に、ホワイトヘッドは量子論の影響を受けて、出来事の「時間的原子性」を強調するようになったと解釈しました(『科学と近代世界』の編纂史参照)。しかし、本当にそうなのでしょうか。このページでは、出来事の個体性と、量子論からの影響をみていきましょう。
|
原子性とは?
|
|
| フォードの研究の強い影響もあって、ホワイトヘッドは量子論の影響下で原子性を強調し時間のエポック理論を説くようになったと理解されてきました。しかし、ホワイトヘッド自身は、時間的原子性という言葉を用いておらず、時間のエポック理論という言い方をしているので、原子性という言葉の意味と、量子論からの影響は、再考してみる必要があります。 | |
| 確かに後期著作では「原子(atom)」や「原子性(atomicity)」という語が用いられているし、「究極的な形而上学的真理は原子論である」(PR)という言明さえ見出せます。しかし、ホワイトヘッドは同時代の論理的原子論や還元主義に反対し、直接経験の複合的な出来事をその哲学の出発点としていました。フォードはホワイトヘッドの原子論をデモクリトスやその継承者らの原子論に比したり、出来事には、ある最小の延長があると記述したりしていますが、ホワイトヘッドのいう原子性は、何か最小量をもつ小さなものでもなければ、すべての複雑なものがそれによって構成されるところの単純で基礎的な粒子のようなものでもありません。むしろそのような原子とは反対に、出来事はそれぞれ複合的な統一体であると考えられており、先取りしていえば、ホワイトヘッドのいう原子性は、現実的なものの個体性ないしは分割不可能性を指しています。ホワイトヘッドのいう原子性は、個体性・分割不可能性とも言い換えられるのであり、出来事が原子的であるとは、部分に分割することができない出来事があるということです。では、ホワイトヘッドのいう原子性を、何か最小量をもつ単純な粒子のようなものではなく、個体性・分割不可能性の意味でとるとき、量子論は何らかの関連性があったといえるでしょうか。 | |
| 20世紀初頭の量子論 | 20世紀初頭の量子論といえば、物理学者たちが空洞輻射の問題に苦心し、その克服から前期量子論を理論的に定式化しようとしていた時期です。温度Tの壁で囲まれた空洞内における光(ないしは電磁波)のスペクトルは、ある振動数までは増加していきますが、極大値となる振動数を越えると減少していくことが、当時、実験的に知られていました。この実験結果は、振動数νが十分小さく温度Tが十分大きいときには、古典的統計力学にもとづきレイリー・ジーンズの公式によって説明できましたが、振動数νが大きくなるときその公式の値も大きくなってしまうため実験結果と一致するものではありませんでした。レイリー・ジーンズの公式に対してヴィーンの公式 は、振動数νが十分大きく温度Tが十分小さいときの実験結果を説明できたため、プランクはこれら二つの公式を理論的に結びつけ、高い精度で空洞輻射のスペクトルの実験結果と一致するプランクの公式を定式化しました。 |
| その後プランクはさらに、エネルギーは無限に分割することができない量だとするエネルギー量子仮説を提唱するに至ります。この仮説にもとづけば、古典的統計力学がもとづいていたエネルギー等分配の法則は一般的には成立しないことが導かれます。振動数νが十分小さく温度Tが十分大きいときには(すなわち、ボルツマン定数をk、プランク定数をhとした場合、kT / hνが十分に大きいとき)エネルギーは連続的とみなせて等分配の法則は成立するとみなせるものの、一般に、振動数νが十分大きく温度Tが十分小さいときには、エネルギーの不連続性が本質的となり、等分配の法則は成立しないのです。 | |
| プランクの量子仮説はニュートン力学やマクスウェルの電磁気学といった古典物理学と相性が悪かったからすぐには認めらなかったのですが、1905年にはアインシュタインの光量子仮説によって支持を得るとともに、次第に理論的に定式化され、ホワイトヘッドがローウェル講義をした1925年には物理学において一定の了解を獲得しつつありました。『科学と近代世界』の特に「量子論」の章や、フォードも参照している1925年4月4日ハーヴァード講義の「原子性」への言及箇所は、ホワイトヘッドがこの物理学の動向を重く受け止めていたことを示しています。この限りで、前期量子論における原子性の発想は、自然内の出来事の連続性を否定し原子性を強いるものであったとも推測できますし、実際、ホワイトヘッドが時間のエポック理論を説くようになった要因の一つだったかもしれません。 | |
| しかし量子仮説の提唱自体は1900年のことであったことに鑑みれば、前期量子論の原子性という発想は、ローウェル講義から『科学と近代世界』刊行の間の1925年に時間のエポック理論が提唱されるようになった決定的要因であったとは断定できません。むしろ、ホワイトヘッドは、前期量子論は、中期自然哲学から論じられている、リズムやパターンの議論、そして、彼のプラトン主義的な思想に影響を与えたのかもしれません。以下、この点をみていきましょう。 | |
|
参考:量子論の哲学的問題
なお、念のため付言しておくならば、出来事の個体性・分割不可性を問題にした量子論の哲学的問題が、この時期のホワイトヘッドに示唆を与えたという可能性はありません。量子論の理論的定式化として今日の物理学者によって認められているコペンハーゲン解釈が一定の地位を獲得するまでには、量子論に含まれる様々な哲学的問題が議論され、そのうちの一つに出来事の分割不可能性という問題がありました。ですが、それが盛んに議論されたのは、『科学と近代世界』刊行よりあとのことであって、量子論の哲学的議論とホワイトヘッドの出来事の個体性・分割不可能性を結びつけるのは時代錯誤になってしまいます。ただ、コペンハーゲン解釈が定式化されるに至るまでの重要な諸理論、例えば1925年にハイゼンベルクによって提唱された行列力学(マトリックス力学)、1926年にシュレディンガーによって定式化された波動方程式、1927年にハイゼンベルクによって提唱された不確定性原理、これらは『科学と近代世界』以降のホワイトヘッドの思索に何らかの影響を与えたのではないかとも推測されますが、今のところ、そのことを確証するような文献は見当たりません。 |
|
| フォードが、量子論の影響を受けたと主張する同時期に、ホワイトヘッドは、無限定なるものから、いかにして有限なものが生じるかという問題を考察していました。特に、問題の核心は、出来事の内的関係から、過去・現在・未来の区別がある外的関係がいかにして生じるかということにあります。時間や空間の外的関係を否定して内的関係から出発する議論においては、内的関係がどこまでも広がっていってしまい、いかにして外的関係が生じるかが問題となります。分割可能性により部分への無限後退に陥ることより、むしろ本質的な問題は、出来事の内的関係と部分‐全体の不可分性を認めることによって、かえって、「いかなる部分もそれ自体、先行する諸部分を伴った全体である」という、全体へ向けた無限後退の問題です。ここには、何か有限なものを知るには無限なるすべてを知らなければならないという問題や、無限定なものからいかにして有限なものが生じるのかという問題が潜んでいます。 | |
| 事実、3月31日に続く4月2日のノートでは「延長量は、固有の矛盾をそれ自体のうちに含んでいるのではないか」という書き出しのあと、ブラッドリーの名前を出しながら時間と空間の非実在性については何か間違っていると記されています。この箇所のあとではカントに言及して部分‐全体関係の問題を論じているが、注目すべきはそこで、「無限定なものは如何にして限定されるのであろうか」と問われていることです。この日のノートによると、「無限なるもの(the infinite)はただ限定されたもの(limitations)において例証される」。そしてこれはピタゴラス(派)の問題であり、ゼノンもまた「生成はいかにして可能か」を問題にしたと書かれています。断片的にしか記されていないにしても、これらの問いをみるならば、この時期のホワイトヘッドが格闘していた問題は、単なる数学や論理学上の問題としての生成のパラドックスや、知覚の幅や量子論の問題に尽きるものではなく、無限に関する形而上学的な問題であったことがうかがえます。 | |
| 出来事が単に内的に関係づけられるだけならば、その関係はどこまでも広がっていってしまうとともに、どの出来事も他の出来事と本質的な区別をもたなくなってしまいます。しかし、何であるか規定されない無限定なるものは現実に存在するものとはいえないのであって、現実的なものの生成には何らかの限定が必要です。この点について同日のノートでは、「我々はシステムを通じて境界のないものを理解するだけである」と書かれ、また、続く4月4日のノートでは「実現が発生的過程(generative process)である」と記されています。ここで「発生(generation)」とは「実現の選択的現実(selective actuality of realization)」であり、ホワイトヘッドは現実的なものの実現を、システムとして、しかも選択を伴う発生的過程として捉えようとしていたとみえます。 | |
| 『科学と近代世界』で加筆される箇所、特に「抽象」や「神」という形而上学的な章がなぜ加えられたかを理解する上で重要なのは、限定を通して現実的なものが生成するとホワイトヘッドが明確に自覚するに至ったことにあるでしょう。4月4日のノートには確かに、フォードが時間的原子性の発見の論拠とする量子論への言及、すなわち「科学においても連続性と原子性は常に[我々に]つきまとっており、量子力学の影響下で原子論的見方が以前にもまして急務となってきた」という記述があります。ですが、この箇所は、より一般的な議論の中で挿入的に言及されており 、この日のノートでホワイトヘッドは、現実的なものと可能的なもの、時間的なものと永遠的なもの、流動的なものと理念的なものを対比的に論じているのです。 | |
| これらの対比は既にローウェル講義でも論じられていたものの、ハーヴァード講義のこの日のノートでは、時間や空間の区別が失われるすべての可能性の場所として常に存在する永遠的な時空連続体について論じられています。これは、すべての可能性の住み家として一切の価値をもたないとされ、しかも「時間は発生にのみ関わる」とも書かれていることから、時間とは対照的に、すべての可能性の永遠的な場所は時間を超越していると考えられています。 | |
| 特に時間のエポック理論の起源を探る上で注目したいのは、ここで、流動的なものと理想的なものとが対比され、古代の数学者たちが強調したように、理想的諸条件は流動の中に例証されるが、しかしそれ自身が流動の中にあるわけではないと記されていることです。この日のノートによれば、数学者は、特殊なものを抽象したときに残されるものを扱うのに訓練されており、「ピタゴラスは、無限について、すなわちいかにして境界なきものが境界づけられるようになるのかということについて悩んだ」。数学の発見者はこの問題を発見したといいます。プラトンは永遠的なものをすべての価値の住み家とみなして錯綜したと解釈されますが、ローウェル講義からも強調されているようにホワイトヘッドにとって価値は限定の所産であり、現実こそ価値です。プラトンのイデアに取って代わるホワイトヘッドの永遠的客体は、永遠的な形ではあるがそれ自体で価値的ではなく、永遠的客体が内在する現実こそが価値的なのです。逆にいえば、価値実現こそが他ならぬ現実の成立であり、形が与えられることによって無限定なものは限定され、現実的なものが生成するのです。 | |
| 既に4月2日のノートでもシステムを通じて境界のないものを理解すると考えられていた通り、ホワイトヘッドは、永遠的客体が合理的体系を織り成すことを通して無限定なものが限定されると考えていました。時間がエポックをなすのは、一つに、過去と未来が現在に同時的に凝集するからだと考えられますが、そう考えるだけではすべてが内的関係になってしまうところ、現実に実現されるものに対して外的な永遠的客体あるいはその合理的体系が、無限定なものに入り込み流動を止め、時間的なものを生起せしめます。逆にいえば、時間的なものの生起は、永遠的客体が織り成すシステムが、ある有限な完結性をもって流動に入り込むことによって可能となります。丸い四角形は現実の存在として実現されえないように、永遠的客体のシステムは、ある合理的な体系として構成されねばなりません。すなわち、そのシステムは、諸部分を経てではなく、諸部分を伴った全体として完結していなければならず、個体的な現実は、個々にまとまりをもったものとして限定されます。色や形などについて、他の永遠的客体の排除を通して、ある永遠的客体のまとまりが選択され、永遠的客体の有限なシステムが完結するからこそ、個体的な現実が生起します。 | |
| この場合、時間はただ無差別に連続的に流れるのではありません。あるまとまりをもったエポックとして時間の単位となる現実が生起せしめられ、それが積み重なることによって初めて系列的な時間が構成されます。最初から連続的な延長があってそれが分割されて時間が構成されるのではなく、ある意味で無時間的な発生論的過程があるまとまりをもって完結しエポック化され、その都度のエポックが積み重なることによって連続的な延長としての時間が構成されるのです。連続的な延長の分割ではなく、個体的な現実の非連続な積み重なりとして連続的な延長が構成されるという考えに転換するときには、ゼノンのパラドックスに陥ることはないし、過去・現在・未来という時間の不可逆性も表現できるようになります。 | |
| 時間的原子性の発見が、現実的なものと可能的なもの、時間的なものと永遠的なものの区別をもたらし、形而上学的体裁を帯びるようになったというのがフォードの筋書きですが、こうしてみてくると、むしろフォードの解釈とは逆なのではないでしょうか。すなわち、ホワイトヘッドは、現実的なものと可能的なもの、時間的なものと永遠的なものが区別されつつもそれらが出会う場において、時間はエポック化されなければならないと考えるに至ったのではないでしょうか。 | |
| そうであれば、ホワイトヘッド哲学の発展史は、中期哲学から『科学と近代世界』刊行に至るまで、時間的原子性の発見という不連続な断絶を強調する必要はなくなります。ホワイトヘッド哲学は、古くはピタゴラス派から続く哲学の伝統の中で展開され、量子論の影響はむしろその展開の中の一つとして跡づけることができます。1925年4月には「思想史における一要素としての数学」の章のもとになる講義がなされており、その章でホワイトヘッドはピタゴラスの学説に立ち戻ったと言っています。ホワイトヘッドによれば、ピタゴラスは流れの中に流れないものを発見し、一般化や抽象化、数の重要性を洞察した人でした 。注目すべきことにホワイトヘッドは、有機体論や量子論について論じてこの章を閉じています。曰く、現存するものは、活動、すなわち基底的なエネルギーの振動する流れが有機化されたシステムである。「音楽の一音符が一瞬には存在せず、やはり具体化されるための周期全体を必要とする」ように、根元的要素を形作っているこのシステムは具体化されるのに周期全体を必要とする。中期哲学やローウェル講義でも、具体的なものはリズムや生命としての有機体であって、それは統一体として分割不可能であると考えられていた通り、ここでもホワイトヘッドは、リズムや周期、システムといった考えから有機体を捉えるとともに、それらによって量子論の現象も説明しようとしていたのです。実際、ローウェル講義を含む『科学と近代世界』の記述は、ホワイトヘッドが、ボーア模型(1913年)や量子条件(ボーアの論文「原子と分子の構成について」が1913年、ゾンマーフェルトによる拡張が1915-1916年)、ド・ブロイの物質波(1923年)といった前期量子論の理論を知っていたことを示しています。 | |
| したがって、もし量子論がホワイトヘッドに何らかの寄与をしたとしても、ピタゴラス派との融合のうちにみることができます。『過程と実在』でホワイトヘッドは、「ニュートンは現代の量子論および量子が振動へと分解されるということに驚いたであろうが、プラトンはそれを期待したであろう」と述べた直後、プラトンの哲学に含まれる次の点を高く評価しています。すなわち、粒子が幾何学的正多面体の形をもつこと、音符間にあるようなコントラストと数的比率との対応、混沌から秩序をもたらす神の概念への洞察です。20世紀初頭の前期量子論では、なぜ原子核の周りを運動する電子はエネルギーを減衰して原子核へと落ち込まないのかということが問題となっていましたが、ド・ブロイの物質波や量子条件、ボーア模型といった説によって電子は特定のエネルギー準位をとって定常状態になるということが明らかになっていました。物質波としての電子は量子条件を満たすことによって定常波となり、特定のエネルギー準位の軌道上で安定に存続することができます。このことは、個々の出来事が分割しては存在しえず、パターンの反復によって安定して存続すること、またエネルギー準位間を遷移する電子の運動変化が非連続の連続として説明されることを例証しています。 | |
| ですが、あくまでも量子的な事象は、特殊な経験科学を一般化した宇宙論・形而上学図式によって説明されるべき例示の一つとして位置づけられるべきであって、ホワイトヘッド哲学の形而上学的発展は、広くはプラトンも含めたピタゴラス派の伝統の中で培われたとみるべきでしょう。『科学と近代世界』刊行に際して加えられる「抽象」の章では、題名通り、現実的なものの抽象として、永遠的客体が織り成す可能的な一般的図式体系が考察されます。その章の最後でホワイトヘッドは「思想史における一要素としての数学」の章における一連の思想に立ち戻ったと言った後、「ピタゴラスに発した考えを敷衍し、形而上学の第一題目として展開してきた」と述べているのです。自身が数学者であり、数学の重要性を終生一貫して力説していたホワイトヘッドは、形而上学を数学的思考の本質のうちに見出していたのであり、この観点から読み解いていくならば、「有機体の哲学」の成立、ならびに形而上学的展開の発展史は、中期哲学から『科学と近代世界』刊行に至るまで、思索の連続的な深化・発展として跡づけられるでしょう。 |