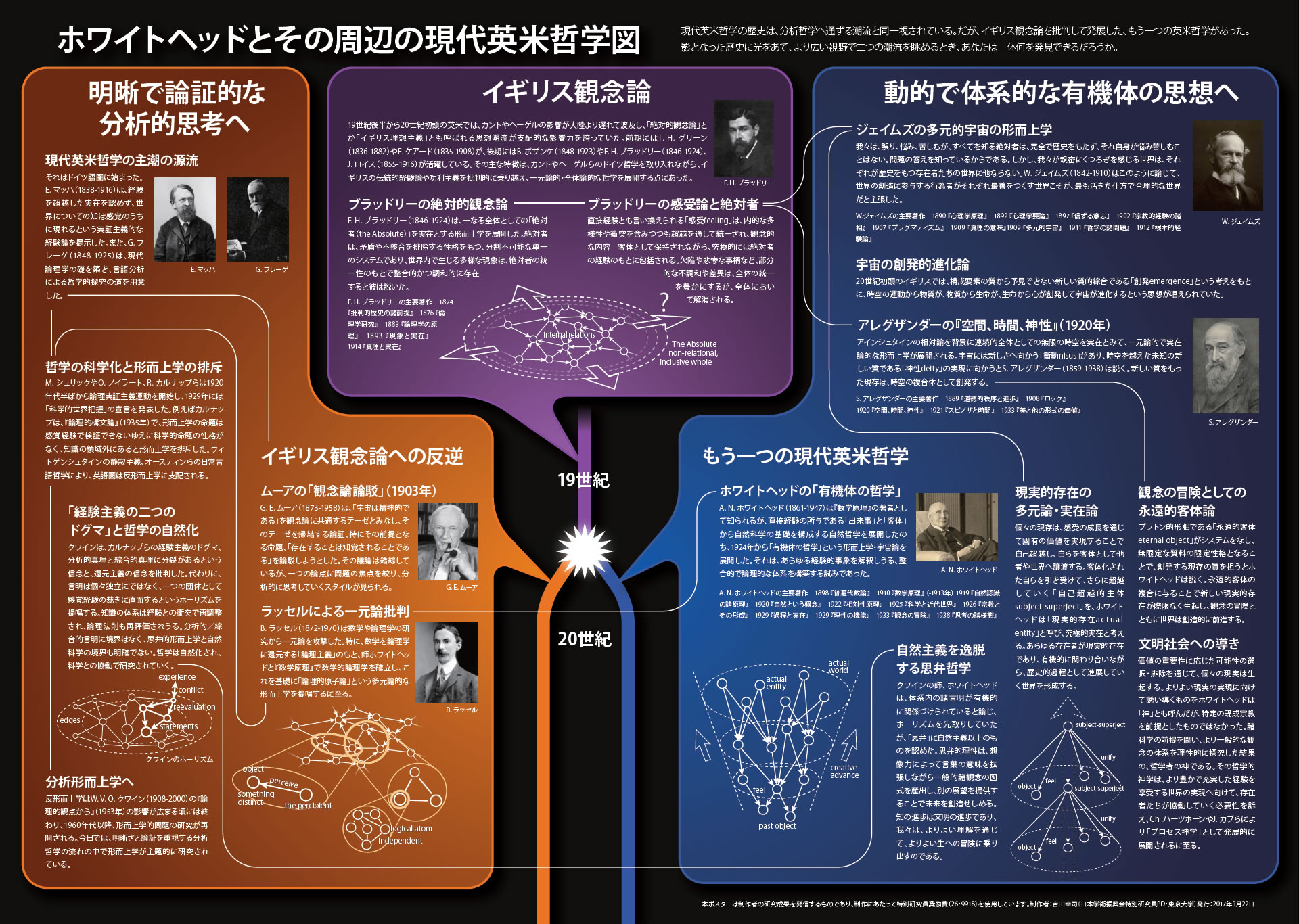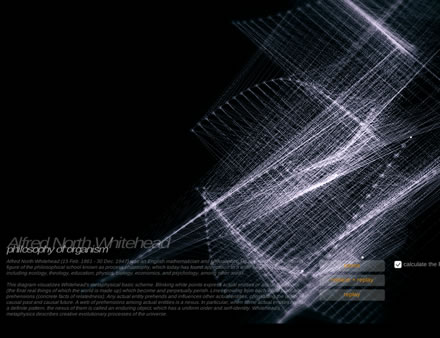自然科学の哲学
ホワイトヘッドが哲学的活動に乗り出した20世紀初頭、自然科学は基盤喪失の状態にありました。非ユークリッド幾何学や相対性理論、量子論の登場により、数学や物理学は変革を迫られ、時間や空間、物質といった基本概念も見直される必要があったのです。数学者・自然科学者でもあったホワイトヘッドは、科学内部から生じた問題をどのように解決したのでしょうか。自然科学と本質的に関わるホワイトヘッドの中期哲学とは、どんな哲学だったのでしょうか。
|
科学の哲学?
|
|
| 「科学哲学」と聞くと、科学について哲学する学を思い浮かべる人が多いかもしれません。科学史や科学の方法論の研究を通して、科学とは何であるか、どうあるべきかを研究するという側面が「科学哲学」の一面にあります(cf. 内井惣七『科学哲学入門』)。また、量子論における観測問題のような物理学の哲学的問題や、進化論についての生物学の哲学的問題など、各専門分野の哲学的問題を論じる科学基礎論を意味することもあるでしょう。少し過去を振り返れば、科学哲学は科学的な哲学“scientific philosophy”を指していた時期もありました。『科学哲学の形成』でライヘンバッハは、哲学は、曖昧さのモヤがかかった思弁ではなく、科学的な知識や論理的分析の方法にもとづかなければならないと主張し、「哲学は思弁から科学へと前進したのだ」ということを示そうとしました。 | |
|
ホワイトヘッドの科学哲学はこれらいずれとも完全には合致しません。確かに『科学と近代世界』や『観念の冒険』などで、科学の歴史や方法論を論じている限りでは、上で挙げた科学哲学の最初の意味を含意していたし、相対論や量子論の哲学的問題を論じる点では、今日の科学基礎論の研究領野を含んでいました。しかし、これらはホワイトヘッドの科学哲学の一面にすぎません。ましてや科学的な哲学など、ホワイトヘッドの念頭にありませんでした(もちろんホワイトヘッドはライヘンバッハの『科学哲学の形成』を読んでいません)。ホワイトヘッドの弟子で、その伝記作家でもあったローは次のように伝えています。
「ホワイトヘッドは、科学哲学を展開したとき、それを形而上学的背景の中に位置づけた。後年に彼は時折、科学哲学(the philosophy of science)というテーマが存在するとは実際には考えていなかったと語っていたほどである」。 |
|
| ホワイトヘッドは、自分の哲学を、“the philosophy of the science”ではなく「諸科学の哲学the philosophy of sciences」と呼んでいます。一口に科学といっても物理学や生物学、心理学、社会科学など様々な分野の科学がありますが、ここで「諸科学」とは、個別諸科学からなる、分科した学としての科学を指しています。そして「諸科学の哲学」という言葉には、同時代の論理実証主義に統一科学への野望があったように、個別諸科学を取りまとめる一つの体系的な知への志向が見出せます。 | |
|
しかし注意すべきことに、ホワイトヘッドは、そうした定冠詞付きの一つの統一的な学があるか自体も問題にしていました。
「[各々の科学に対する]科学の哲学(the philosophy of a science)は、様々な思考からなる複合体に浸透しその複合体を一つの科学にする統一的性格を明白に表現しようと努めるものである。[すべての科学に対する]科学の哲学(the philosophy of the sciences)は―それが一つの主題とみなされる限り―すべての科学を一つの科学として提示しようとする努力なのである。あるいは、―それができない場合―そのような可能性の反証である。」 |
|
| 物理学の哲学や生物学の哲学など、各専門分野についての科学の哲学があることは認められるにしても、諸科学すべての哲学については、「それが一つの主題とみなされる限り」という但し書きが付されており、そのような哲学が存在しない可能性も暗示されています。むしろその場合、諸科学を統一する哲学の可能性の反証が科学哲学の主題になると考えられているのです。 | |
| ホワイトヘッドの科学哲学は、科学全体の知がいかにして成立するかの探求であったといってもよく、彼はそれを、自然科学の再構成を通して遂行しようとしました。つまり中期のホワイトヘッドは、「諸科学の哲学」のうちでも心の哲学や社会科学の哲学などを除外し、「自然科学、すなわち主題が自然であるような諸科学」に考察の焦点を絞っていたのです。したがって、中期に限れば、ホワイトヘッドの科学哲学とは、自然科学の哲学であり、広くは自然哲学であったといってもよいでしょう。『相対性原理』では、倫理学や神学、美学とは関係をもたないと宣言された上で、「それはましてや形而上学ではない。それは汎物理学(汎自然学“pan-physics”)と呼ばれるべきである」と語られています。この“pan-physics”という言葉は、今日でいう物理学の諸部門(熱力学だとか電磁気学だとか)すべてという意味ではなく、むしろ自然学全般というほどの意味でしょう。この少しあとには次のようにも書かれています。 | |
| 「科学の哲学(the philosophy of science)は次のような事実によってどの特殊な自然科学とも異なっているに過ぎない。すなわち、科学の哲学とは、それを様々な部門に分けることが有用となる前の段階の自然科学である、という事実である。この哲学は、我々が分化の過程を始める前に言及されるべきことがあるから存在するのだ。」 | |
| 現在の科学は、個々の専門領域をもつ分科した学を指しますが、科学の語源である“scientia”は、もともと、体系的な知を意味していました。自然科学の哲学に限定されるホワイトヘッドの中期哲学も、分科した個別科学についての哲学ではなく、自然学全般の体系的な知を求める“pan-physics”としての自然哲学を企図していたのです。 | |
|
とりわけ自然科学の中でもホワイトヘッドが考察の端緒としたのは、物理学や幾何学でした。『純粋理性批判』においてカントは、ニュートンの自然哲学の成功を背景に、客観的に妥当する(今日でいう)科学的な知がいかにして成立するかを問いましたが、この点においてホワイトヘッドはカントと対照的な状況にありました。科学的な知の哲学的考察という点では両者には共通の問題があったといえますが、ユークリッド幾何学やニュートン物理学を確固たるものと想定していたカントとは異なり、ホワイトヘッドは、むしろそれらの瓦解に直面していたのです。『プライスとの対話』では次のように記されています。
「我々は、物理学で重要なことはほとんど全部知られている、と考えていた。もちろん、いくつかはっきりしない点があって、放射線の現象に関する奇妙な変則性もその一例であるが、これも物理学者たちが1900年までには解決してしまうだろう、と思われていたのである。確かにその通りになった。しかし、そうなる際に科学全体がめちゃめちゃになり、永遠の視座に確固たる位置を占めていると思われていたニュートン物理学が消え失せてしまったのである。いや、それらは、ものの見方としては有用だったし、今なおそうなのであるが、しかし、実在の究極的記述としては、もはや妥当ではない。確実性が消失したのである 。」 |
|
| 冒頭でも触れた通り、科学の基礎は、非ユークリッド幾何学や相対論、量子論の登場によって揺らいでいたのであり、幾何学や物理学の再構成こそがホワイトヘッドの課題となっていました。自然科学のうちで最も基礎的である物理学に諸科学を還元することには反対でしたが、諸科学の哲学を論じる上で物理学の哲学的再構成は中期哲学の中心的な論題だったのです。 | |
|
究極的な与件としての直接経験
|
|
| さて、このように理解される意味での自然哲学を展開する際にホワイトヘッドが究極的な拠り所としたのは、我々の直接経験でした。この点で、現象学、特に『ヨーロッパの諸学の危機と超越論的現象学』で生活世界への立ち返りを訴えたフッサールと問題意識を共有していたことも指摘されます(田中裕『ホワイトヘッド』講談社)。ホワイトヘッドも中期の時点では形而上学的思弁へ踏み入らず、事象そのものへ立ち返り、感覚を通じて直接経験されるがままの自然を記述する立場をとっていました。『数学原理』を共に築きあげたラッセルが、複雑な文を最も単純な原子命題へと分析し、それと対応する世界の原子的な事実に実在をみる「論理的原子論」を唱えたのに対して、ホワイトヘッドはむしろ、最も直接的な、しかも未分化で複雑な経験的事実を究極的な与件としたのです。それを言い表す用語が「出来事(event)」です 。中期哲学は、直接に与えられる未分化で複雑な出来事を抽象していくことを通して、時間や空間といった自然科学の基本的諸概念を導き、自然科学を基礎づけようとしていたのです。 | |
| こうした出来事を根本に据える中期自然哲学によれば、分析される以前の直接に経験される自然の事実は様々なタイプの諸要素に多様化されていません。我々は「木々の緑」や「鳥たちの囀り」、「太陽の暖かさ」を個々ばらばらに一つ一つ知覚しているのではなく、それらが未分化の直接的事実(fact)を知覚しています。この限りの自然の事実は明確な境界線をもたず、不尽的性格をもちます。例えばみなさんが部屋の中でこのページをみているとしたら、みなさんの知覚している事実には、ドアや窓の隙間からかすかに入り込んでくる音や風の知覚などが(たとえ意識的に知覚されていないとしても)含まれているでしょう。 | |
| 科学的研究を含め自然研究とは、この直接経験される自然の複雑で未分化の事実を多様な諸存在へと分析していくことに他なりません。単純な要素がまず与えられてそこから複雑な事実が構成されるのではありません。むしろホワイトヘッドによれば、分析の仕方が異なれば、タイプの異なった諸要素へと多様化されるのであり、「全自然は(様々な仕方で)諸事物の複合体として分析されうる。かくして全自然が諸出来事の複合体として分析され、全自然が感覚所与の複合体として分析されうる」。様々な諸要素へ分析するこの過程をホワイトヘッドは「自然の多様化」といいます。自然哲学は、自然とは異なるタイプの意識などを関係づけて考察する「異質的な」思考を差し挟むことなく、自然内で知覚される「同質的な」構成要素をそれら自身の間で関係づけ、自然の事実を整合的に説明しようとする試みです。実証的な自然科学も、自然の複雑な事実をより単純な概念によって整合的に説明しようとしているのであって、「科学の目標は複雑な事実の最も単純な説明を探し求めることである」。 | |
| 自然科学や自然哲学に関する限り中期のこうした立場は、後期においても一貫しています。「有機体の哲学」を打ち立てた『科学と近代世界』では、近代の科学的唯物論は、死せる物質を究極的な実在として、物質がただ配置をかえるだけの意味も価値もない世界像を作り上げたと批判されます。我々の直接経験の事実はおろそかにされ、本来、意味や価値を含んでいるはずの我々の自然の直接経験を思考において抽象し、その抽象されたものを具体的なものと取り違えてしまったというのです。これをホワイトヘッドは「具体者置き違えの誤謬」として非難しますが、ここには、我々の直接経験の第一義性と、抽象による分析的思考という科学の特徴づけが見出せます。ホワイトヘッドはロマン派詩人たちの詩句、例えばワーズワースの「分析せんがために殺す」という詩句を引用しながら、意味や価値を含む我々の直接経験への回帰を訴えるとともに、自然の複雑な出来事を出発点として「有機体の哲学」を展開します。 | |
| 「有機体の哲学」の内実は別のページを参照して頂くとして、ここでは方法論のみを一般的に特徴づけておきましょう。ホワイトヘッドは、未分化で複雑な直接経験の事実を具体的なものとし、それへと立ち返ることを強調しました。その一方で、具体的なものを単純な諸要素へと抽象・分析することを科学の方法論の特徴として挙げていたのです。ホワイトヘッド自身の中期自然哲学も、具体的な自然の事実から抽象化を通して、自然科学の基本概念を導く限りではその例外ではありませんでした。そして、その自然哲学の最も基本的な概念が、「出来事」と「客体」でした。次のページでは、「出来事」について解説します。 |